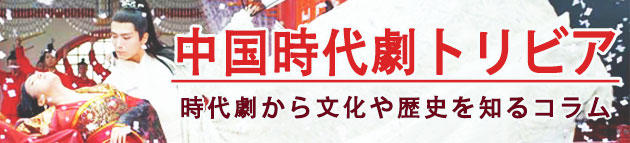
中国では「ハンコ」っていつからあるの?|中国時代劇トリビア#131
中国歴史ドラマの中に登場する、なんだか気になる“アレ”のトリビアを探るこのコーナー。今回は、フー・イーティエン×チャン・ジンイー共演の愛と成長の物語「惜花芷~星が照らす道~」に関する気になるあのことを紹介!
「惜花芷」にも登場! 中国では「ハンコ」っていつからあるの?

「惜花芷~星が照らす道~」©2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.
ドラマ「惜花芷~星が照らす道~」で、主人公・花芷が手作りお菓子を売るときに、ハンコを捺したオリジナルの紙包みを使っており、とても可愛らしくて印象的でした。劇中で登場するようなハンコは、中国ではいつ頃からあったのでしょうか?
参考文献の「ハンコの文化史」の解説によると、台北の国立故宮博物院にある「殷鉩」が最も古いハンコとされているそうですが、中国における考古学上の発掘による実物の中から確認できる最も古いハンコは、周時代末期(BC480-22年)のものだそう。その頃の使い方としては、財産や大切なものを守るために、封泥といわれる粘土塊に、ハンコを捺して封印をほどこしていました。
これが漢代の後期に入り、中国で紙が開発されると、ハンコにも色々な変化が見られるようになってきます。今までは、粘土塊に捺すものだったので、大きさにも制限がありましたが、紙に捺すようになったことで、大きさの制限の必要がなくなり、ハンコの寸法は次第に大きくなっていきます。サイズが大きくなったことに加え、平面の紙に捺すようになったことで、印面の内容も変化して、戦国時代から秦漢時代に見られたという画像印(肖形印)から文字が彫られるようになり、形も円いものから正方形や長方形になっていったそうです。
紙の出現についで起こったハンコの大きな変化は、紙にハンコを捺す際に、朱泥(朱肉)を使うことがあげられています。朱泥は、朱砂ともぐさを混ぜて水、または油で練った粘着力のある印肉のこと。朱は年月を経ても変色しないので、古くから中国で万古不易(永久に変わらないこと)の象徴として尊ばれたそうです。
【参考文献】
新関鉄哉著 吉川弘文館 『ハンコの文化史 古代ギリシャから現代日本まで』
日本放送出版協会『ハンコロジー事始め 印章が語る世界史』
提供:エスピーオー/BS12 トゥエルビ
発売元:エスピーオー 販売元:エスピーオー
https://www.spoinc.jp/official/sekikashi/

Text:島田亜希子
ライター。中華圏を中心としたドラマ・映画に関して執筆する他、中文翻訳も時々担当。Cinem@rtにて「中国時代劇トリビア」「中国エンタメニュース」を連載中。『中国時代劇で学ぶ中国の歴史』(キネマ旬報社)『見るべき中国時代劇ドラマ』(ぴあ株式会社)『中国ドラマ・時代劇・スターがよくわかる』(コスミック出版)などにも執筆しています。
\アジア俳優名鑑 バックナンバー/


記事の更新情報を
Twitter、Facebookでお届け!
Twitter
Facebook